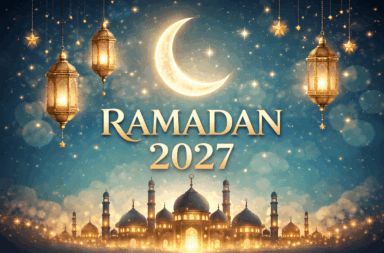日本が果たすべき役割と、世界に示す「食」の未来像とは
2050年、世界人口は約97億人に達すると予測され、食に関する課題は複雑かつ緊急性を帯びたものになっていきます。ダイバーシティ、サスティナビリティ、食糧確保──この3つのキーワードは、未来の食卓を構成する中核となる要素です。
世界の共通課題は「どのように食を守り、つないでいくか」。その中で、日本という国が国際社会の中でどのような存在感を示し、未来の食の課題にどう貢献できるかは今後重要なテーマになっていくと考えています。

世界中でダイバーシティはますます加速していく
世界的に多文化共生の流れは加速しており、様々な食への配慮は今後ますます重要になってきます。宗教や信条、健康・アレルギーなどに応じた食の提供は、企業・行政・観光にとって“対応すべき選択”ではなく“前提”となりつつあります。そのような未来を見据え、世界中で多くの食品製造メーカーや飲食店がフードダイバーシティに取り組んでいます。
人口増と地球温暖化
地球温暖化に伴う異常気象、土地や水資源の劣化、生物多様性の喪失。これらはすでに農業や漁業の現場を直撃しており、もう元に戻ることも難しい状況下となっています。さらに、世界人口の増加により、今後30年間で現在の1.5倍の食料供給が必要になると見込まれています。
国際情勢不安下での食糧確保
ウクライナ情勢、国際的な物流の混乱、新型コロナの影響──近年の不安定な情勢は、世界の食料流通を直撃しました。特に輸入依存度の高い国ほど、深刻な影響を受けています。
日本の食料自給率(カロリーベース)は38%(2023年度 農林水産省)。この構造は、早急な見直しが求められています。今後は以下のようなアプローチが必須です:
-
都市農業やスマート農業の普及
-
食品ロス削減とフードバンクの強化
-
国内外での持続可能な調達連携
日本は世界に何を提供できるか
2050年を見据えたとき、日本の役割は決して「規模」で勝負するものではありません。むしろ、高品質・高信頼という独自の強みをどう活かすかが問われます。
例えば:
-
少量多品目で栄養バランスを取る和食の知恵
-
食材を無駄なく使い切る「もったいない」文化
-
動物性食材に頼らなくても、出汁や発酵の技術で食の満足度を実現
こうした「日本が古来から培ってきた食の価値」は、今世界の共感と尊敬を呼ぶ資源と言っても過言ではありません。
未来の食卓に“責任ある選択”を
2050年の食卓は、気候、宗教、技術、政治、倫理──あらゆる要素が交差する「世界の縮図」になります。
サステナビリティは“選択”ではなく“責任”に、
ダイバーシティは“配慮”ではなく“前提”に、
食糧確保は“輸入”ではなく“共創”に。
この3つの視点を統合して、未来の食卓をどう描くか。そこにおいて、日本は「食の質」と「共生の精神」で、国際社会に新たな道筋を示すことができます。
未来を生きる私たちが、今できる選択とは何か。提供する一皿の向こうにある、地球と人間の未来に目を向ける時が来ています。